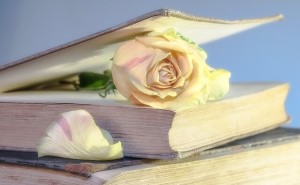LINEやメールなどで文字を入力する時に、「ぁ」「ゎ」など、字を小文字に入力する人がいますよね。
わざわざ小文字にするのには何か理由があるのか、小文字を使う人の心理を見てみると、その人があなたに対して思っていることも知れる可能性があります。
小文字を使う人の心理にはどんな心理があるのでしょうか?
今回は、小文字を使う人の4つの心理を説明します。
可愛く思われたい
小文字を使う人の心理で一番多いと言えるのが、「相手に可愛く思われたい」という心理です。
小文字で入力することで文字自体が可愛らしい印象を与え、自分に対しても「可愛い」と思ってもらえるだろうという意識。
顔を合わせての会話であれば仕草や態度で可愛さを表現することができますが、実際に会っていない状況の中で可愛さを表現することは難しいものですよね。
そのために、小文字を利用して可愛さを表現し、相手に「可愛い」と思ってもらいたいと感じているのです。
これがもし異性にだけにするやり方であれば、その人は計算高い人と言えるかもしれませんね。
相手に可愛いと思ってもらうことによって自分を恋愛対象として見てもらいたい気持ちが出ているため、多少の計算が隠されています。
同性同士でも小文字を使うという人であれば、皆に可愛いという印象を与えたいのであり自分のイメージを作っていると解釈することができるでしょう。
若いと思われたい
10代で小文字を使う場合は、まだ理解することができるでしょう。
皆がやっているから、当たり前のように使っているからという理由で小文字を使っている分には同世代では受け入れられます。
しかし20代30代と年齢が上がるにつれて、小文字を使うことに違和感を覚えるようになっていく。
そうした中でも小文字を使うという場合は、「若く見られたい」という思いがあることも考えられるでしょう。
例えば、LINEやメールをしている相手に年下が多いという場合、「世代が違う」「おばさん」と思われたくないと思ってしまいますよね。
年齢が違うとしても、警戒されたり距離を置かれたくないために相手に自分が合わせるという行動をとる人もいるのです。
要は相手に「若い」と思われたいために、小文字を使っているという状況。
その人なりに、相手に合わせたり寄り添った形の手段であるため、否定することは傷つけることに繋がってしまいます。
他の人と差をつけたい
小文字を使うことによって、相手は多少なりとも「ん?」と関心を見せますよね。
普通の文字じゃない、他の人とは違うといった印象を受け、何度も見たり読み返したりする。
他の人と同じじゃつまらない、もっと意識して見てもらいたいという思いでいる人は、印象に残る小文字を使うこともあるのです。
読みにくい、幼いといった印象を与えるかもしれない小文字ですが、使っている人よりは使ってない人の方が多い。
そのため、他の人との差をつけることができることから、あえて小文字を使うという人もいるでしょう。
「自分は特別」「周りと一緒にしないで」という思いが隠されており、特別視してほしいと相手に訴えている状況と言えます。
目立ちたがり屋や積極的な人に見られる意識で、他の人との差別化を図っているのでしょう。
近付きたいと思っている
自分は小文字を使わないけど、相手が小文字を使ってくるという状況もありますよね。
それが異性であるという場合もあるでしょう。
もしあなたのもとに小文字を使ったメッセージが異性から送られてくるというケースであれば、「近づきたい」「距離を縮めたい」と思っていることも考えられます。
相手の男性が女性に対して小文字を使うということは、親近感を持ってほしいという心理でいることが多く、そこにはあなたとの距離を縮めたい思いがある。
可愛らしさ、女性らしさを、メッセージの中に男性がいれることによって、女性の警戒心を解こうとしているのかもしれません。
例えば男性からのメッセージで、絵文字もない、句読点もない文章が送られてきたら、「冷たい」「怖い」「男って感じがする」と距離を感じますよね。
こうした思いを持たせない為に、わざと可愛らしい小文字を使っているとしたら、男性に悪気がある訳ではありません。
あなたともっと親しくなりたい、もっと親近感を持ってもらいたい、警戒心を解いてもらいたいという思いで小文字を使っていることも。
本当に親しくなったり心を許せる間柄になっていけば、その男性は徐々に小文字の使用を控えるかもしれません。
まとめ・小文字を使う人の4つの心理
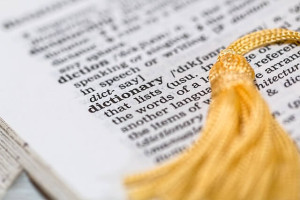
小文字を使う人には、可愛らしいといった印象を持つ人もいれば、幼い、面倒くさいと感じる人もいるかもしれませんね。
しかしどんな思いで小文字を使っているかまで見ていくと、その人の隠された思いや自分への気持ちを知ることができることもあります。
また関係性によっても変化が見られるもの。
親しい仲や頻繁にやりとりする仲になれば、小文字を使うことがなくなっていくこともあるでしょう。